伊藤 廸子(いとう みちこ)
弁護士

プロフィール
東京大学法学部(1970年)およびワシントン大学ロースクール(法学修士)卒(1974年)。
1972年に日本の弁護士資格を、1976年にニューヨーク州の弁護士資格を取得し、日米両国で法律実務の出来る最初の弁護士となる。買収・合併、合弁事業、ライセンス、戦略的提携、販売提携、不動産取引などの取引法と、会社の設立から解散までの手続きを含めた会社法を専門とし、主として米国に進出している日系企業に助言してきた。
東京およびニューヨークのいくつかの法律事務所勤務を経て、1989年から2016年末まで、モリソン・フォースター事務所のパートナーを務めた。2001年4月から、日本の伊藤・見富法律事務所のパートナーを兼任。
著作物に、『アメリカ駐在員のための法律常識』(有斐閣、1984年)、『アメリカ進出企業の法務マニュアル』(有斐閣、1987年)、『米国の不動産取引案内』(有斐閣、1989年)、『アメリカの民事訴訟』(監訳)(有斐閣、1995年)、『アメリカのM&A取引の実務』(有斐閣、2009年) などがある。
今私は、ニュージャージー州イングルウッドの自宅で愛犬のタシャとのんびり生活している。7年ほど前に、夫が亡くなったのと事務所の定年退職年齢に達したのをきっかけに、当時パートナーとして所属していたモリソン・フォースター事務所を退所し、45年にわたった弁護士生活に終止符を打ったのだ。
生き馬の目を抜くと言われるほど競争の激しい、マンハッタンの大手事務所のパートナーとしてキャリアを終わらせることができたことで、私は企業法務弁護士としては一応成功を収めたといえるだろう。ここまでたどり着く道は決して平坦ではなく、多くの友人や、幸運に支えられてきたことはいうまでもない。
幸運にも渉外弁護士に
私の弁護士としてのキャリアは、「社会貢献したい」とか、「人権を守らなければ」、という高尚な理由で始まったわけではない。夫や兄弟など、誰かに頼って生きて行くしかない女性の姿をまぢかに見て、どんな状況下でも自分の力で生きていけるよう、一生続けられる仕事に就きたいという思いは、子供のころから持ってはいたが。ごく普通のサラリーマンの家庭に育ち、世間知らずだった私は、国文学を勉強したいと思い文学部に入学したのだが、すぐに「文学部を卒業しても、助手や助教授になれるのは男子学生だけ。他の道を探さなければ」と気づかされた。当時、ほとんどの企業は大卒女子の採用をしておらず、女性が一生働ける仕事を手にしようと思ったら、資格を取るか公務員になるしかなかったのだ。そこで私は、資格試験や公務員試験を受けるのに有利と考えられた法学部に転部し、4年の時に司法試験に合格した。
私は、人付き合いや駆け引きが得意ではなかったので、裁判官になろうかと考えていたのだが、民事裁判の研修の時に、裁判所長に「女は裁判官にはなるな」と言われた、裁判官になると頻繁に転勤がある、世間とのかかわりが制限されやすい、などの理由で裁判官になることは断念した。検察官も、裁判官同様頻繁に転勤があることから気乗りがしなかったので、消去法で弁護士になることを選択した。選択した、というよりは、それしかなかった、というのが正しいかもしれない。弁護士になってもすぐに独立できるわけではないので、就職先を探さなければならなかったが、男女差別が激しかった時代、駆け出しの女性弁護士を雇ってくれる事務所はなかなかみつからなかった。私が司法研修所を卒業したころは学生運動の余韻が強く残っていた時代であり、若い男性弁護士の多くが、「アメリカ資本主義の片棒はかつぎたくない」として、渉外事務所を避ける風潮があったためか、人手不足になった渉外事務所が採用してくれた。その後、渉外弁護士業務の人気が高まり、渉外事務所に採用されるのが難しくなったことを考えると、私がこの時に渉外事務所に入所できたのは、ある意味幸運であったと言えるだろう。
アメリカへ留学
この事務所で、日本で事業活動をしている英国や米国の企業に対して、日本法(主として企業法務)に関する助言をしたり、英語の契約書の交渉・作成などをしたりしているうちに、英語、そして英米の企業・経済法について勉強することの必要性を感じさせられた。事務所の先輩弁護士も全員アメリカ留学経験者である。そこで事務所から許可を得て、シアトルにあるワシントン大学のロースクールへ留学することを決めた。
このワシントン大学での一年間は、私の人生の中でもっとも勉強した一年間といえるであろう。すごい量の判例の要約とそれに対する自分の批評を、学生たちの前で発表させられるので、それまで図書館で勉強をしたことがほとんどない私が、ほぼ毎日夜中まで図書館に引きこもって勉強をしたのである。一夜漬けのできない課題にとりくみ、宿題の多く出る講義に出席したことで、アメリカの法律に対する知識と英語力を培うことができた時期であった。
ワシントン大学に滞在した期間、勉強に追われながらも、遊ぶことも忘れたわけではなかった。冬休み中に留学生向けに催されたスキーツアーに参加し、そこで後日結婚することになる、フランス人の留学生と知り合ったのだ。

結婚-人生の転機
ワシントン大学から法学修士号を取得した後、1974年9月に私はニューヨークへ移動した。日本で勤務していた事務所からの依頼で、マンハッタンにある法律事務所で一年間、日本法のアドバイザーとして働くことが決まっていたからだ。日本に進出していたアメリカ企業の本社の法務部に、日本法の下での注意事項を助言する人材が必要とされていたからである。
私はニューヨーク、彼はシアトルという、超遠距離恋愛(片道約4000キロ)を続けながら、その年のクリスマスイブに、私たちはマンハッタンのシティホールで簡単な結婚式を挙げた。たまたま出張でニューヨークに来ていた裁判官の友人が立会人になってくれた。たった3人の結婚式だった。
結婚後もしばらくは、ニューヨークとシアトルに分かれての別居生活が続いた。その間、2人で将来どこで生活すべきかを話し合った。選択肢は、日本、フランス、アメリカ、あるいは全く別の場所。お互いに公平になるようにと、結局アメリカに住むことに。もともと一年間の留学の予定が、気がつけば、アメリカに定住することになってしまったわけだ。仕方なく東京の事務所に退職願を出した。
ニューヨーク州司法試験を受験
東京の事務所に退職届を出すと同時に、勤務の傍らアメリカでの就職活動をはじめたが、状況はかなり厳しかった。第一次オイルショックの不況の最中、日本女性の弁護士の求人などあるはずもなかった。アメリカ企業の法務部や法律事務所に、仕事探しの手紙を200通ほども書いたが、面接に来いという回答をもらったのはごくわずかで、面接まで行ったものも、冷やかし半分に呼ばれたに過ぎないものが多かった。また、日本人、それも女性は特に数が不足しているから入りやすいだろうと言われて、国連・世銀などの国際機関にも応募したが、弁護士は不要と言われ、すげなく断られてしまった。こんな面接で味合わされる屈辱感にいい加減嫌気がさしてきた。そんな時、私と同じような立場で働いていた日本人弁護士が「アメリカの法律学位を持っていなくても、ニューヨーク州の司法試験が受けられるようだから、やってみないか」と言ってくれたのだ。その人は特別に受験資格を認められたフィリピン人の作成した嘆願書のコピーをくれて、「ぜひやりなさい」と熱心に勧めてくれた。正直なところ、私は試験はもう御免だという気持ちが強かった。しかし背に腹はかえられない。それに落ちたってもともとじゃないか。そう腹を決めた私はそのコピーをもとに嘆願書を作成し、ニューヨーク州の最高裁判所に提出した。
嘆願書を提出して2ヶ月ほどたった4月末。なんと、「貴殿に本年7月に施行される司法試験に限り、受験資格を与える。」という通知が来た。それで慌てて、仲間の弁護士に教えられた特別講座(クラムコース)を受講し、試験に備えた。試験は1975年7月22、23の両日にわたって行われた。日本の司法試験と異なって、出題範囲が極めて広かった。契約や不法行為などの一般法のほかに、税法、保険法といった技術的、専門的なものまで含まれているのだ。私は全くの準備不足で、知らない事項がかなりあったが、日本法の解釈に基づいて回答を書いたりして、何とか白紙でだけは返却しないようにした。時間不足もあって、法律用語のスペルを間違えたりしたので、受かるとは全く考えもしなかった。
そうこうしているうちに、私の契約の終了時期を迎えたが、私の必死の嘆願が功を奏し、事務所でもう六ヶ月だけ私を雇ってくれることになった。ただし、「弁護士」としてではなく、「パラリーガル」として、しかも給料も今までの1/3ということであった。給料が減っては、それまで住んでいたところにも住めないので、単身の女性専用の、家賃が格安でかつ食事付きのアパートに移った。まさに“小公女”の境遇に置かれたわけである。
就職先が見つからないまま、シアトルに戻って大学院で勉強する準備をしていた12月初め、一緒に司法試験を受けた友人が「君も受かったよ」と言って、合格者の名前の記載された、ニューヨークタイムズを見せてくれた。私が司法試験に受かると、それまで勤めていた事務所で、「司法試験に受かるくらいだから仕事はできるのだろう」ということで、正式に弁護士として雇ってくれることになった。
ここでも私は周囲の人の支援と、運に恵まれたのである。私に司法試験を受けることを勧め、嘆願書の見本を下さった方の存在、それと、私がシアトルに着いた直後に連邦最高裁判所が、外国人が司法試験を受けることを認めない州法は憲法違反という判決を下した、というタイミングの良さである。この友人がいなかったら、そしてこの判決が出るのが少し遅かったら、今の私はなかったかもしれない。
企業法務弁護士として活動
ニューヨークの事務所で働けることになったことで、すべて順調に行ったわけではない。その後も幾度となく、偏見と差別と戦わざるを得ない場面に遭遇した。外国人と全く仕事をしたことのない同僚の弁護士から、「スピーチセラピーを受けて、アクセントを取ってこい」と言われたことも度々あったが、その都度じっと耐えてきた。人の嫌がる仕事を一手に引き受けてやっているうちに、その分野の専門知識を蓄えることができて良かったと思っている。何度も日本へ帰ろうと考えたが、その都度、「ここでネを上げたらアメリカに残ったかいがない」と考えて思いとどまった。

幸運にも、私がニューヨーク州の弁護士として勤務し始めてから間もなくして、日本企業の大規模な米国進出が始まり、私の生活も多忙をきわめるようになった。企業やオフィスビル、リゾートホテルやゴルフ場などの買収案件が次々に入ってきて、目が回るような忙しさだった。いわゆるバブルの時代の到来であった。それまで海外投資の経験が全くなかった経営者が、アメリカの資産を買い漁る。当然そこには危険がともなってくるわけで、その危険を未然に防ぐのが我々弁護士の仕事であった。私の役目は、法律について助言するにとどまらず、「訴訟好きな契約社会アメリカ」と「人の和を重んじる日本社会」の違いを説明するなど、文化大使的なものも兼ねていた。日本企業の米国への投資が盛んになると、日本企業をクライアントに欲しいアメリカの法律事務所は、積極的に日本人の弁護士を採用するようになった。そのおかげで私も数回ヘッドハンティングをされ、幸運にも大手事務所のパートナーとなることができたのだ。
バブルは長続きせず、その後いわゆる「失われた30年」に突入し、日本企業の米国からの撤退が続くのだが、その撤退を法務の面から支援するなどの仕事が結構あったのと、日本企業を巻き込んだ数件の大型の訴訟のサポートの仕事がかなりあったのとで、私は職を失わず、無事に定年退職を迎えることができたのだ。
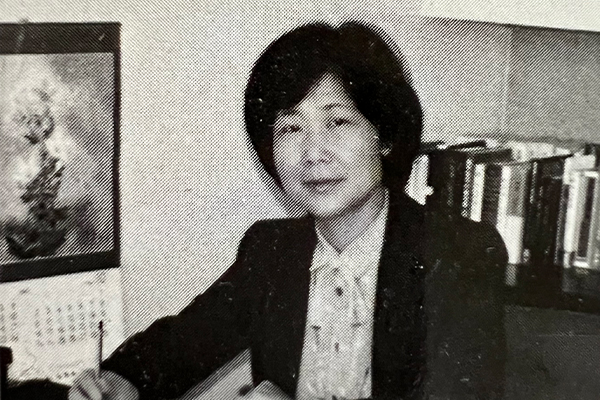

家庭とキャリアの両立
これはアメリカに限られた問題ではないと思うが、多くのプロフェッショナルな女性は、「若いうちに子供を作るか」それとも「一応成功して自分の地位が安定してから子供を作るか」という選択を迫られるようである。「男性を含め、限られたポジションを争うのに子供がいたのでは不利になる」というのが後者を選択する女性の言い分になる。それに対して、責任のある地位について、例えば法律事務所であればパートナーになってから、子育てのための休暇を取ることはクライアントの為にならず、また仲間の弁護士にも迷惑をかけるのでよくない、という批判がされている。また、安定したポジションについた時には、どんなに早くても30代後半になっているから、子育ては体力的に大変だという意見もある。どちらが正しいかは分からない。私の周りを見ても、若いうちに子供を作る人、安定したポジションを得てから子供を作る人が半々ぐらいである。
私自身は、体力があるうちに子育てをした方が楽ではないかと考え、ニューヨークで弁護士業務を始めてすぐに出産した。当時私はニューヨーク、夫はシアトルという生活であったことに加え、私も夫も単身でアメリカに留学してきたので、子育てに家族の協力が期待できない状況であった。一抹の不安はあったが、それでも早く子供が欲しいと言う思いが強かった。
アメリカの大都市では、プロフェッショナルであると否とにかかわらず、両親が共働きというケースが多く、そのため家庭と仕事を両立させやすい環境が整っている。子供を預けて仕事をすることを批判するような風潮は全くないし、両親が仕事をしている間に子供を預けられる託児所が充実している。ニューヨーク市内には、公立の託児所が200ほどあり、お金はかかるが、私立の託児所も多数存在している。0歳児も安心して預けられる施設も存在している。会社の敷地内、あるいは近くに社員のための託児所を設けている企業も少なくない。また、アフタースクールプログラム(学校の放課後のプログラム)も充実していて、親がいなくとも子供たちが楽しめるようになっている。また、教師との面談などの学校行事も、働く親たちが参加しやすいように、夜の6時あるいは7時ころから始まることも多く、こうした面でも、仕事と家庭を両立させやすくなっている。私は、託児所、アフタースクールプログラム、ベビーシッター、夫(大学で教えていた夫は、シアトル、ニューヨーク、シカゴと移動し、息子が高校に入学したときに最終的にニューヨークに移住)を何とか使いこなして子育て期を乗り切った。契約交渉が長引いて徹夜になりそうなときは、息子を事務所に連れてきてそこで寝かしつける、急な出張はできる限り断る、など色々苦労した。特に大変だったのは、息子を車で学校に送ってから事務所に着いたとたんに、学校から、息子さんがけがをしたあるいは熱を出したからすぐに医者に連れて行くように、という電話が入った時で、その時は本当に泣きたくなった。
アメリカの家電製品も、仕事と家庭を両立させるのに一役買っているといえよう。まず冷蔵庫・冷凍庫が大きいので、野菜など特に傷みやすいものを除いて、一週間分の買いだめができるし、料理なども作り置きをして冷凍し、電子レンジで解凍して食べることができるという便利さがある。また、洗濯機も容量が大きいので、一回にたくさん洗濯でき、さらに乾燥機があるので、洗濯物を干す手間がかからない(ニューヨークでは、ベランダや庭先に洗濯物を干すことはアパートの規則や地域の条例で禁じられていることが多い)。また、食洗器を使えば食事の後片付けが楽である、など手間が省けるようになっている。私が何とか家事と仕事を両立させることができたのも、こうした家電の手助けがあったからだと思う。
後進の皆様に
後進の皆様の何かの指針になれば、と私のこれまでの行き当たりばったりの生き方を紹介させていただきましたが、時代と環境、個人を取り巻く状況によってこのような生き方が通用するか、同じような結果が得られるかは異なってくるということを理解していただきたいと思います。ただ、自分から行動しないと何もかわらない、あきらめずに何かにしがみついてがんばれば、運命の女神が微笑んでくれるということをお伝えしたいと思い、本稿を執筆させていただきました。
